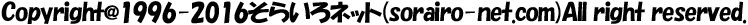|
| [和名・種類] |
ナガニシ |
| [学名] |
Fusinus perplexus |
| [英名] |
- |
| [名前の由来] |
長螺。
別名、ヨナキ(夜鳴き)。 |
| [分布] |
北海道〜九州 |
| [科名] |
巻貝綱(腹足綱)バイ目(新腹足目)イトマキボラ科 |
| [特徴・生態] |
水深10m〜40mの、砂泥底に生息するイトマキボラの仲間。
殻は長さ約14cm、径約4cmになります。長紡錘形で、螺層は10階、あまり厚くはありませんが、質は硬いです。上方の螺層には8本〜9本の強い縦肋があり、多くの細い螺肋があります。体層は丸く、長い水管が下方へ出ます。表面は濃桃色ですが、黄色のビロード状の殻皮で覆われています。蓋は革質で、黒褐色です。
卵のうをサカサホオズキといいます。 |
| [感想] |
僕の貝殻コレクションの中にもある貝殻のひとつ、ナガニシです。タコツボや網などに引っ掛かることがあるのかな?漁師さんの船揚げ場のところに落ちていました。でも、その時にしか見付けたことがないなー。
ナガニシは少し深いところにいる貝みたいだから、漁師さんが捨てたりしないと手に入らないかもしれないなー。表面は毛が生えているような感じで、あんまり綺麗じゃないけど、大きな貝殻だったのでかなり嬉しかった(^^)。食用にもなる貝らしいのですが、関東ではあまり食べないのかな? |
| [写真撮影] |
2006年12月13日 |
| [関連ページ] |
|
|
|
 |