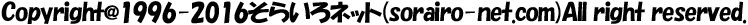| [���O�E���] |
�E�}�X�M�S�P |
| [�w��] |
Polytrichum commune Hedw. |
| [�p��] |
Hair cap moss |
| [���O�̗R��] |
�n���ہB |
| [���z] |
���{�e�n�A�k�����̉��ђn��ɍL�����z |
| [�Ȗ�] |
�X�M�S�P�ȃX�M�S�P�� |
| [�ԐF] |
���F�i�t�F�ΐF�Ɍf�ځj |
| [�Ԋ�] |
�T���E�U���E�V���E�W���E�X�� |
| [�����E���] |
�@��n�`���R�т̂�⎼�n��j�t���тɕ��ʂɐ����Ă���X�M�S�P�̒��ԁB
�@��^�̃R�P�ŁA�s�͂قǂ�Ǖ��}�����A������10cm�`20cm�ɂȂ�܂��B�s�͍d���A�j����ɂȂ�܂��B
�@�t�͔�j�`�ŁA����6mm�`12mm�ɂȂ�܂��B��������Ək�ꂸ�Ɍs�ɖ������܂��B�╔�������t�g�S�̂����ɔ��ŕ����܂��B
�@�E�q�̂����͊p����ɂȂ�܂��B������5cm�`10cm�ɂȂ�܂��B�Y���̗Y�ԔՂ͎O�p�`��䚗t�̊Ԃɑ����̗Y�킪�ł��A�����ɐ��q���l�܂��Ă��܂��B
�@���Y�ي��ł��B
�@���s�Ȃǂ̘a���뉀��ے�ł����Ƃ����ʂɎg�p�����R�P�̂ЂƂB�ǂ������I�I�X�M�S�P���ے�Ɏg�p����܂��B����ł̌������͍���ł��B���̂ق��ǂ������߉���ɁA�R�X�M�S�P�A�Z�C�^�J�X�M�S�P�Ȃǂ�����܂��B |
| [���z] |
�@����[�A�d�ېA���̌������̓T�b�p���킩��܂���ˁ[�B�L�m�R�Ɠ������A�R�P�̓���ɂ͋�J���܂��B��J���Ă������Ȃ�܂������A��J�͂��邯�nj��������t�Ȃ��Ƃ������Ƃ�������ł����(^^;)
�@���Ԃ�X�M�S�P�̒��Ԃ��Ǝv���܂��B�X�M�S�P�̒��Ԃ͑ے�ɗ��p����邱�Ƃ������̂ł����A���R���ł͈ӊO�ƌ������Ȃ��A���ł��B�쐶��Ԃ̃X�M�S�P������ɂ́A���R�L���Ȏ��n�тȂǂɍs���Ȃ��ƌ��t���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��ł��ˁB
�@�g�߂Ō������邱�Ƃ̂ł���R�P�̒��Ԃ́A��ނ������Ă���݂����ł��B����ł���������̂������ł���[�B�ǂ������������������Ă���̂��A�ǂ��킩��Ȃ��āE�E�E�B�}�ӂ����܂�o����Ă��Ȃ����B |
| [�ʐ^�B�e] |
2008�N04��02�� |
| [�֘A�y�[�W] |
|