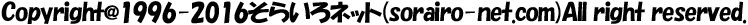| [a¼EíÞ] |
c^ |
| [w¼] |
Parthenocissus tricuspidata |
| [p¼] |
Boston ivy |
| [¼OÌR] |
ÓB`¢¤«¿ðªµ½àÌB
ʼAicd^iÄÓjBERMÈÌLd^ªíÎÅtd^i~ÓjÆÄÎêA»êÉεÄt·é½ßicd_ÆÄÎêéB
ʼAA}dià jB½ÀãÉ÷tðÏlßÄá¿ðìÁ½±Æ©çB |
| [ªz] |
kC¹`ãBA©N¼A |
| [ȼ] |
uhEÈc^® |
| [ÔF] |
©ÎFitFÎFÉfÚj |
| [Ôú] |
UEV |
| [Á¥Eðà] |
@RìÌÑàâÑɶ¦éAtÂé«áØB
@Ǫ}µAß©çæ[ªzÕÉÈÁ½ª«Ð°ðLεA÷²ââÇðãèÜ·B÷çÍFÅ·B{N}ÍÔF`©FųÑÅ·BÛ¢çÚª½ èAZ}ªBµÜ·B~èÍ·³1mm`2mmÌ~`Å·BèØÍFÅA3Â`5ÂÉÈèÜ·BtÍÙÚ~`Å·B
@Z}©ç·³3cm`6cmÌWUÔðoµA©ÎF̬³ÈÔð½Â¯Ü·BÔͼa2mm`3mmÅAÔÙÆYµ×Í5ÂÅ·B
@tÍ2` èAÔÌÂZ}ÌtÍå«At¿Í·³ñ15cmÉÈèÜ·BtgÍ·³ÆÍ5cm`15cmÌL`ÅAãÍ3ôµAôÐÌæÍsƪèAÉÍæªäÉÈéÜÎçȪ èÜ·BîÍ[¢n[g`Å·B¿ÍââúAÙÚ³ÑÅ·BÔÌ©Ȣ·}Ìtͬ³At¿àZ¢Å·BØêÝÌÈ¢àÌ©çA1ô`3ô·éàÌA3¬tÌà̪¬¶èÜ·B
@ÊÀͼa5mm`7mmÌ
`ÌtÊÅ·BHÉFÉnµA\ÊÉÍ¢²ªÂ«Ü·BíqÍ·³4mm`5mmÌ|`Å·B
@EVÈÌc^EVÉÇĢܷªAc^EVÍs©çt
ªðoµA¼ÈÊðæ¶oèÜ·B¨ÌÇÊâ»Éí¹ÄAVÎâgtðyµÝÜ·B |
| [|[g] |
@c^ÌtÌÊ^Å·B
@c^Ì¢nÈÊÀÌÊ^à Á½ñÅ·ªAtÌÊ^Ìûª©ª¯éÌÉð§Â©È[ÆvÁÄAÊÀÅÍÈAtÌÊ^ɵܵ½BÅàA൩µ½çAÊÀ¶áÈÄÂÚÝÈñ¶áÈ¢©EEEB»ñÈ^âà èܵÄBÂÚÝÈÌ©AÊÀÈÌ©A©ªÅàÇí©çÈ¢ÜÜfÚ·éÌàÇÈ¢©È[ÈñÄl¦à èܵÄB
@Yñ¾ÉAc^ÌtÌÊ^ðfÚ·é±Æɵܵ½B
@c^ÌtÌÔÉ©¦éÎFÌcucuACÔǤݽ¢È̪AÂÚÝ©ÊÀÌÇÁ¿©Å·B±êªÂÚÝÈÌ©AÊÀÈÌ©A½x©ÊÁIJ×ÄÝæ¤ÆvÁÄ¢½ñÅ·ªAÏ@µÄ¢é¤¿Éª±»¬ èæçêĵܢܵ½(^^UB¤[ñAȺ©í©èܹñªAÁèÌA¨ð¯¶êÅÏ@µnßéÆA èæçêéæ¤ÈCª·éEEEBsRÒªtÌAÉBêÄ¢éÆ©ÁÄvíê½Ì©ÈH
@sRÒƨᢳêÈ¢æ¤ÉA¼DÆ©ñ©çÔ纰Ľûª¢¢Ì©ÈHÊ^ðBÁÄéÆAßÌlªöæb»¤Èçű¿çð©Ä¢éüð´¶éñÅ·æË[B |
| [Ê^Be] |
2008N0615ú |
| [ÖAy[W] |
|