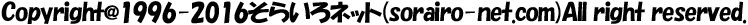|
|
浄土宗のお寺です。五劫山天養院宝泉寺といいます。
1559年(永禄2年)に建てられたお寺です。幾度か修復を行い、本堂は250年前の建築で、堂内は丸柱だそうです。
もちろん読んだことはありませんが『新編相模国風土記稿』によれば、和田義盛の鬼門の鎮守として建立されたそうです。本尊は行基作の薬師像だそうです。
ご本尊の薬師像は、和田義盛の身代わり薬師といわれています。和田合戦のとき、総身に負傷した和田義盛が痛さを感じずに一同が不思議な思いをしたそうです。その時、この薬師像の顔から胸に傷ができ血潮が流れていたと言われています。
これを見て、薬師像の加護を念じ、大いに戦ったといいます。
以前、古本屋さんで『新編相模風土記稿』を見付けたことがあったんですが、その時、買えばよかったなーと今でも悔やんでいます。たしかその時は5000円くらいだったかなー。
 三浦半島の歴史:人物事典・和田義盛 三浦半島の歴史:人物事典・和田義盛
 三浦半島の歴史:1213年・和田義盛の乱 三浦半島の歴史:1213年・和田義盛の乱 |
|
|
薬師如来と両脇時立像は神奈川県の指定文化財になっています。
木造一木造で、彫眼、平安時代の作です。薬師如来は74.5cm、脇時の日光菩薩は110.5cm、月光菩薩は112.5cmです。
この像は、もともとは和田義盛邸宅の鬼門守護に建立された安楽寺の本尊だったものを、昭和18年に天養院に移されました。
薬師如来は右腕を屈して、胸前に挙げ、左手を膝上に置いて薬壺を掌上に置いています。
左右の両脇侍は、中尊に対して外側の腕を上げ、ともに左右の手で棒状のものを握るかのような形をとっています。おそらく日輪月輪の付いた蓮茎を持っていたものと思われます。
三像の単純な顔立ち、頭部と体とのバランス、翻波風の衣文線などから、平安時代の早い頃の特色を良く残しています。
薬師三尊を守るように、室町時代の十二神将があります。像高62cmの寄木造で、玉眼嵌入の立像です。
ちなみに安楽寺は浄土宗のお寺で、山号を仏照山といいます。国道拡張工事のため、昭和18年に廃寺となってしまいました。
|
 天養院本堂入り口 天養院本堂入り口 |
 バス停和田下車 バス停和田下車  徒歩5分 徒歩5分
天養院内  |
|
他にも、和田義盛の肖像彫刻があります。江戸時代の天保年間の作品と伝えられる武者姿の木像です。
板仏もあります。板仏は平板を薬師如来型に切り抜き彩色したもので、出陣の際に鎧びつに入れて武運長久を祈願したといいます。
三浦氏の丸に三引の文のある和田義盛の位牌もあります。
大きく立派な屋根の上には三浦氏の家紋、丸に三引があります。やはり三浦氏とゆかりの深いお寺なんですね。本堂入り口にも丸に三引の家紋があります。
|
|
|