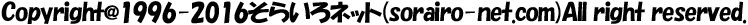|
第三大臼歯・智歯を親知らずと呼びます |
| |
大臼歯の最後方にある第三大臼歯(智歯)のことを、一般的に「親知らず」と呼びます。
他の永久歯がすべて生え揃った後、20歳前後で生えてきます。
6歳臼歯(第一大臼歯)、12歳臼歯(第二大臼歯)に比べて小さく、形は変化に富んでいます。 |
 |
正しく生えない親知らず |
| |
生えてくる位置、傾き、時期など、個人差が大きいといえます。
下あごの親知らずは前へ傾いていたり、水平になっていたりすることが多く、上あごの親知らずは後ろ向きに傾いていることがあります。 |
 |
親知らずの埋伏歯 |
| |
親知らずの生える場所が十分に得られない場合には、歯冠の全部、あるいは一部が埋伏した状態になることがしばしばあります。
さらにあごの骨の発育不全やスペースの不足が原因で、先天的に欠如する頻度も高いと考えられます。 |
 |
虫歯の原因にも |
| |
親知らずは歯列の一番奥にあって、歯ブラシが届きにくいために歯のまわりが不潔になりやすい状態になります。とくに歯冠の一部が埋伏した状態では、歯冠と歯茎との間に細菌が繁殖して歯冠周囲に炎症を起こす智歯周囲炎を起こしたり、虫歯になったりします。 |
 |
顎関節症の原因となることも |
| |
生えてくるスペースの関係上、親知らずが噛み合わせに参加することはあまり多くありません。
せっかく生えてきても、前方の歯を圧迫し、不正咬合の原因となることもあります。
また、傾斜や位置の異常により、下あごの動きを制限し、あごの関節の病気である顎関節症 の原因となる場合もあります。 の原因となる場合もあります。 |
 |
経過観察か抜歯 |
| |
正常に生えてきて何も障害を与えない場合は、とくに処置を必要としません。しかし、たびたび炎症症状を引き起こしたり、隣の歯や歯列に悪影響を及ぼしたりする場合には、抜歯が選択されます。 |